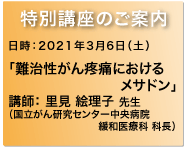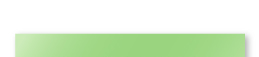
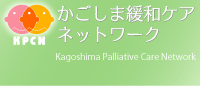
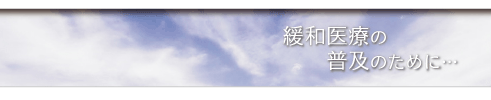
トップページ > 緩和ケアに関する情報 > 宗教的ケア
![]() 坊さん奮闘記5 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
坊さん奮闘記5 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
■入院で自ら患者体験
今回は私自身が患者になった話である。
実は、入院は六月ごろの検査で決まっていたが、主治医が二週間ぐらい必要だというので延び延びにして、十月半ばにようやく患者になったという次第である。
以前、院内研修の講師をしたり、実際にケアチームに参加したこともある病院で、顔なじみのスタッフも多いが、今度は足を踏み入れたことのない循環器科への入棟だった。
実際、パジャマ姿になってみると、自分自身の気持も、病院の光景もいつもとは異なるとはよく医療者の間で話されているが、本当にそうだと思う。トータルペインとはよく言ったもので、いろいろなことが胸をよぎる経験を私自身も家族もすることになった。
その一方で、私自身と他の患者さんとの関係にも変化が起こった。かねてから医療側の人間と見られているが、今度は同病相憐れむ仲間となった。
■同室の仲間らと交流
私の病室は四人部屋で、二人の先輩患者がいた。入院初日、何かにつけてぎこちない私と妻に、いろいろとやさしく教えてくれた。
二日目は、これから始まる検査や治療について情報を与えてくれた。三日目になると、お互いの素性を語り合う中で、私の職業を問われた。縁起でもないと思われるのではないかと多少の不安もあったが、思い切って僧侶だと話してみた。
喜んでいいのか悲しんでいいのかわからないが、とてもそうには見えない、明るい坊さんだねと二人は笑ったので安心した。それからは、私たちは多くのことを語り合った。病気のことについても、三人ともつとめて明るく話したが、ことばのはしばしには不安や心配があらわれた。なおさら、明るい話題をさがし合った。
■明るさの中ににじむ不安
四日目の朝、隣の患者さんが、奥さんに電話をかけて来たと言う。そして、隣の坊さんに葬式のことは頼んであるから、心配しなくていいと告げたら驚いていた、と笑った。
私は彼の心中を思った。離島の病院から、冠動脈三本のバイパス手術のために転院してきて、奥さんは、片道十時間船に揺られて通ってくる。数日後、奥さんと会ったが、あら、聞いてた通り坊さんには見えないと笑い、遠い所だけど本当に来てくれますか、という。私は、もちろんと答えて、ただもう少し焼酎でも飲んでからにしようと話した。彼の退院の日、もう飲む場所も決めてある。私の退院の後、手術前後も数回病室を訪れた。彼の退院も間近である。長い付き合いになりそうである。
もう一人の先輩患者は見掛けよりはるかに重症である。十メートルしか歩くことは許されていない。それでも発病までの武勇伝をよく話題にした。そして、最後に必ず、もう二度とできないねと話した。
彼の奥さんは、結婚以来外で働いたことはなかったそうだが、発病後、五十三歳で初めて働きに出たという。毎日、夕方スニーカーで通ってくる。
私の入院五日目、彼と奥さんは医師に呼ばれた。死刑の宣告を受けてくるよ、と病室を後にした。
一時間ほどして、いつもとは違って、だいぶ沈んだ様子で二人は帰ってきた。半年後、大手術ということになったという。年に一例か二例しかない手術で、術後障害が残る確立が高いといわれた。そうなってまで、何のために生きるんだろうねと、彼は力なく笑った。
■会話が励ましになることも
その夜、私と彼は遅くまで話した。私との会話が、その時励ましになったかどうかはわからない。ただ次の日、私のいない時、私の妻に、昨夜は飛び降りて死のうかと思ったが、ご主人と話て、少し明るくなれたよ、と話したそうである。
私の退院の日、二人はエレベーターまで見送りに来てくれた。そして声をそろえて、すぐに帰っておいでと笑った。私も手を振って、必ず会いに来ますと笑って答えた。
約束は守っている。
■沈黙の共有にも大切さ
年末年始のこの時期になると世間は何かにつけてにぎやかである。人の気持も高揚し、私も例にもれず、寺の住職として除夜や元旦の行事に追われる。
そんな折、ふと作業の手を休めて病院で出会った方のことを思う。
ある方は外泊で久しぶりの自宅を楽しんでいる。しかし、症状からすると家族そろっての最後の正月になるかもしれない。ある方は外泊もままならず、病室でこの時期を過ごす。またある家族は、去年は一緒に過ごせたのに、今年はその人のいない正月を迎えている。
世間のにぎやかさは、もう一方の相反するものをも際立たせてしまう。
それも諸行無常だという理はわかるが、心のうちの切なさは如何ともし難いとは、ある患者のことばである。
さて、数年前のこの時期に一本の相談電話を受けたことがある。この電話は、その後の相談活動に大きな示唆を与えてくれることになった。
最初、その電話は無言で始まり、十五ぷん程続いた。その間、何度も呼びかけてみたが応答はない。しかし、耳をすますと息遣いは聞き取れた。いたずらかとも思ったが、その日の私は気分が良かったのかもしれない、待ち続けた。しびれを切らして、申し訳ないが、あと三分したらこちらから切ります、と告げた。その時間が過ぎようとした時、「あなたも我慢強い人ですね」と女性の声がした。「ほめてくださってありがとう」と応じた。
それから、有言の相談が始まった。中身は男女の仲だった。これまでの経緯を話したうえで、「別れたものかどうか迷っている、ぜひ、意見を聞かせてくれ」という。
こんな時、私は私なりの答えを出すことはしない。いくら誠実に答えても、それはあくまで私自身の判断基準によるものにしかならない。
■事実ではなく感情を聞くこと
それでも答えをせまるので、私はこう話した。「話をうかがってみると、あなたにとってその方はとても良い人で、別れるのは辛い。でもこのままでは、いいとも思えない。その両方で心が揺れているのが今の状態ですね」
すると、「本当にそうなんです。わかってくださってありがとう。実は数日前二度と会わないと告げてきたのですが、辛かったのです」という。すでに答えは出ていたのである。
そして、もう一つ相談があるのです、と話し始めた。
■本当に深刻な相談は後から
「私は近々大きな手術を受けます。だいぶ進んだ悪性のものです。二年前、兄がやはり悪性の病気で死にました。私の人生は一体何でしょう。何のために生きているのでしょう」。そういった意味のことを、時折、泣きながら長いこと話し続けた。最後になって、「今泣いています。長いこと無言で、しかもどうでもいい男と女のことを一所懸命に聞いてくれて、私の勝手な恨みにこんなに時間を割いてくれて本当にありがとうございます。うれしかった。この電話の間、私の人生は充実していました」と話した。そして、続けて、「これから晴れた日の病室から夜空を見上げて、一番輝く星があったら、あなただと思っていいですか?」
私は思わず。「星になります」と言ったら、彼女は笑い出した。そして、星になんかならないで、いろんな人の相談に乗ってくださいと電話を切った。
沈黙の時間を共有すること、事実でなく感情に焦点を当てて聞くこと、問題を整理すること、答えのある程度出た手みやげ相談の後、本当の深刻なことが顕在化することなどは、病室でも応用している。
名前を名乗ることもなかったが、あの彼女は今ごろどうしているのだろうか。笑顔を浮かべてくれていると良いが・・・・。
■短いが必要だった五日間
現在、私は自分自身のグリーフワーク(悲しみの作業)の最中である。
暮れも押し迫った十二月十五日、無二の親友K君が脳出血で突然倒れたという知らせを、講演先の長崎で受けた。聞いた時驚きはしたが、それ程深刻には考えず、帰り道の運転中も、回復にはどれほどの時間が必要だろうか、障害が軽ければいいが、などと思っていた。
鹿児島に着くと、真っすぐ彼の病室に駆け込んだ。そこには、機械につながれた彼と、四人の沈み込んだ学業途中の子どもたちの姿があった。
奥さんが、自発呼吸がなくなったと話した。思わず涙が溢れそうになった。
その時、子どもの一人が、「お父さん、長倉さんが来てくれたよ」と呼びかけた。彼を凝視していた私は、はっとして、彼に大声で話しかけた。そして、酔っぱらって寝ているときと同じ顔だな、と言うと子どもたちが目には涙を溜めていたが、声を上げて笑った。私は、自分の役割を自覚した。彼の愛する家族を私なりに支えること、それが私の彼に対する看病だと思った。
しばらくして、主治医から説明があるというので、家族の依頼で一緒に聞いた。懇切な説明だった。しかし、精いっぱいのことはするが、希望は持てないとのことだった。私はあえてたずねた。「先生のご経験で、この状態から回復した患者はいますか」。医者は首を振って、ない、と答えて、文献では見たことがありますが、と付け加えた。私たちは、大きな絶望と針の穴より小さい希望を感じた。
■無二の親友の心停止まで
それから五日後、私は所用先から帰るのを待っていたように、着いて間もなく彼の心臓が停止した。今にして思えば、家族や周りにいる者たちが事態を受け容れるための、短いが必要な五日間だった。
その間、家族や私たち友人は、彼も黙って聞いているかのように、べットサイドで若いときの武勇伝などを話した。時折笑い声を上げるので、とうとう看護師に注意された。救急の病棟で不謹慎と思われたらしい。私たちは、ごめんなさいと全員で謝った後、それがおかしくてまた笑った。
だれも悲しくない者なんかいない。誰か一人が泣き出せばみんな泣き叫んでしまうことはお互いに分かっていた。泣くのはもっと後でいいと耐えていた。私たちは話しながら、あらためて彼とのつながりの深さを確かめていた。自然に回想療法と予期悲嘆の相互ケアとをしていたのである。
彼の葬儀は、身内と友人たちでしめやかに営んだ。一週間後、彼は眼科の医院を開いていたので、医院と友人たちとの共催で偲ぶ会を企画した。その際、追悼の冊子を作った。ここに抽文を転載することを許していただきたい。
「降りしきる雪の中で君の葬儀の二日後、所用で機上の人となりました。うって変わって晴れ渡った空の下、雪の霧島山系が眼下に見えた途端、僕の記憶は一気に三十六年前のあの日に戻りました。そう、高校一年の晩夏、君とN君と僕との三人で、無謀と言われても仕方のない、それでいて気持だけはいっぱしの登山家気取りで歩いたあの日のことです。疲れ果ててしまった僕たちは下山もならず、山の鞍部で野営する羽目になり、何度もテントを吹き飛ばされそうになりながら、不安を打ち消そうとするかのように、大声で歌ったあの時から、絆が強くなったのでした。それから、いろんなことがありました。あのN君が二十六歳で突然命を終え、今度はこんなにも早く君が。僕はあの山でおいてけぼりをくわされた気分です。
窓からもう一度見下ろすと確かに見えたのです。あの時の疲れ果てた顔ではない君とN君が笑顔で手を振り、そして確かな足取りで雪の上に足跡を残しながら歩く姿が。
いつになるかわからないが、お土産を持って君達の足跡を必ず追いかけるよ。そしたら又あの時のように歌おう。待っていてくれ」
■思いの言語化で胸少し落ち着く
彼が死んで一ヶ月余り、私はまだ時折涙ぐむ。しばらくは続くのだろう。しかし、思いを言語化することで少し胸が落ち着く。彼が最後に残してくれたものは、これからの病棟に出かける僧侶としての私の人生に大きく影響を与えることになるだろう。
■無財の七施も時にありがた迷惑
ある日「心が病気でひねくれてしまったんだろうか」と私に問いかけた肝ガンの患者さんがいた。どうしたんですか、とたずねると「あんたは無財の七施って知ってるか」と言いながら、紙に書かれたものを見せてくれた。
そこには、眼施(あたたかい眼差し)、和顔悦色施(にこやかな表情)、言辞施(やさしい言語)、身施(精いっぱいのおこない)、心施(いつくしみ深いこころ)、床座施(人にあたたかい席を)、房舎施(気持よく迎えるこころがけ)とあった。
「お医者さんも看護師さんも、見舞いに来てくれる人たちもこんな気持で来てくれてるのは重々分かっているけれど、とれてるから、文句も言えないし、なお辛い。今日は愚痴だと思って聞いてほしい」と言う。
■本当に患者の側に立っているか
「まず、眼施っていうけど、おれと目を合わせる前に肝臓の辺りを見ているような気がする。ガンをあたたかい目で見てくれてもあんまりうれしくないよ」
「和顔悦色っていうけど、おれが深刻なことを言うと、そんなこと考えるなと怒るか、作り笑いを浮かべるかのどちらかだよ」。私はドキッっとした。ぼくもそうですが、と恐る恐るたずねると「当の本人に向かって言うわけないだろう、あんたは脳天気だよ」と大笑いしたのでほっとしたが、内心複雑だった。続けて「ただでさえ暗いところにもう一つ暗いものを持ってくるのは勘弁してほしいよ」。今度は真顔になった。
「言辞施だってそうだよ。見舞いに来た人は、病気の話しかしないんだよ。同じこと、何度も言わされるは辛いよ。それに一番おれの嫌なことだもんな」
「次の身施だって、何かしましょうか、と言われたとき、いらないよと言うと相手が悲しそうな顔をするんだよ。あれはたまらないね。だれだって放っといてほしいときもあるだろう」と言う。私は愛想笑いをするしかなかった。すべてに身に覚えがある。
心施についても、やさしさが辛いときもあるという。だれかが来ると知らせがあって、身を起こして待ってると、着いた途端に、寝ていれば良かったのにと言われる。思いやりなんだろうけどね。そういえば、あんたは、起きててくれたんですね、ありがとうと言ったよな。ほんというと、涙が出るくらいうれしかったんだよ。私は胸が熱くなった。
床座施だっていえばうれしいことがあったよ。転院したとき、着いたらすぐに看護師さんが、納豆嫌いなんですってね、ここでは出しませんから安心してくださいって。そこまで知ってくれているんだと思ったら、ここにすべて任せようという気持になったんだよ。それに、坊さんまで呼んでくれるしね、といたずらっぽく笑った。
■耳が痛かった病床からの指摘
最後に、嫌みなことばかりでごめんと言うので、私は、耳の痛いことが多かったけど、いい勉強になりましたと、本当に素直にお礼を言った。
最初に会ったとき、あんたは何があっても逃げませんよ、と言ってくれた。だからなんでも話せたんだ。ああ、さっぱりした。今度は、あんたの説教を聞かせてくれよ。
以来、彼の病室に行くのが楽しみになった。私の思いは今も同じだが、もう病室には彼の姿はない。だが、彼は。私の中に生きている。
■辛く悲しい時が僧侶の出番
最近になって、うぐいすがきれいな声で鳴き出した。
この連載を始めたころにも鳴いていたから、早いもので一年が過ぎたことになる。
当初は、この十数年の間に病棟で出会った患者さんやそのご家族、私も含む医療スタッフの様子を気軽に書いてほしいとの編集子の依頼で始めたが、最終稿になってあらためて読み返してみると、期待に答えられたかどうか心許無い。それどころか、私の身の回りにも予想外のことが起こり、それに心を奪われてしまった様子が反映してしまっている。もう少し、計画的に書くべきであったと反省している。
弁解ついでに少し生意気をいうと、なあんだお前のやっていることはこの程度のことか、と感じていただけたら望外の喜びである。しょせん、寺務の合間に出かけているぐらいのことでしかないのはもうお気付きだろう。だったら、病院にいる門徒さんや檀家さんの所に自分も行ってみようかと思い立っていただけたら本当にうれしい。
そのうえで、グリーフケア(編集注・喪失から生じる悲嘆に対する支援)としての視点がある通夜、葬儀、法事が営まれると、仏教に対する評価はもっと違ったものになると期待している。葬式仏教と揶揄される現実は承知しているが、私は葬式仏教その通りです、と答えることにしている。一番辛くて悲しい時に出かけるのが私の仕事です、とビハーラ活動を通じて考えるようになったのである。
■医療と宗教が自然に手を携える日夢見て
最後に、医療と仏教がどのように協力するのかということに少し触れておきたい。
実際の医療現場の多くがどうやったら治癒できるかというところに重きが置かれていることは否めない。そして、私自身が病棟に出かけるようになってなおさら、多くの医療スタッフはそのための教育を受け、研究し、実践に励んでいることに心から頭が下がるようになった。しかし、患者さんに死が訪れることは考えたくないから、意識の外に遠ざけようとしてしまう。しかし、人間には百パーセント訪れる現実から逃げることはできない。だから、ターミナル期の患者さんに対する心のケアには戸惑うことになる。
そこで、仏教はどう考えるかというと、生老病死を自然なことと受け容れる。忌むべき死さえも、仏になる機縁とし、大いなるいのちの世界に帰る営みと考える。
この両者は、普通に考えれば相反する思想である。実は、臨床的には私はこのままでいいと思っている。なぜなら、正義が二つ主張されると争いになるのは自明のことだが、二つの正義がどうしたら共存できるかと模索するのが仏教ではなかったか。病棟の中で、さまざまにそれぞれの人生観を根底にして議論が行われることこそ、マニュアル化されるより健全な姿に思える。患者さんも家族も医療スタッフも自灯明、法灯明を手がかりに人生の歩みを進めるのだから。
■患者さんとその家族を中心に
私には夢がある。
緩和ケア病棟であろうと、急性期の病棟であろうと、これから進むであろう在宅医療の現場であろうと、患者さんとそのご家族を中心に、医師や看護師、ソーシャルワーカーとともに、僧侶が一緒に、温もりと笑顔の中でお茶を飲みながら語り合う光景が自然になることを夢見ている。
うぐいすがまた鳴いた。ある老婦人から、「うぐいすは何と言って鳴いていると思いますか」と問われたことがある。ホーホケキョですかと答えると、「あれは法を聞けよ、と鳴いているんです。仏法を聞こうとしない私へのお誘いですよ」と話してくれた。以来、私も仏様の呼び声と思っている。倶会一処の皆さまに合掌します。