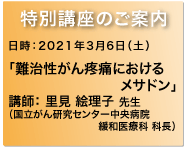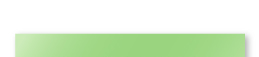
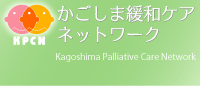
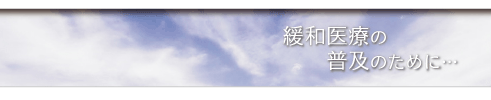
トップページ > 緩和ケアに関する情報 > 宗教的ケア
![]() 坊さん奮闘記4 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
坊さん奮闘記4 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
■患者家族のケアも大切
病棟に出入りするようになって、患者さんの家族もケアの対象であるということにあらためて気付かされた。病の当事者である患者さんの問題がクローズアップされやすいが、たんに介護者としての補助的役割を期待される存在としてだけの家族像ではなく、身内に病人を抱えてさまざまに葛藤している家族には、WHOのいう精神的、社会的、スピリチュアルな痛みが現われる。
看病疲れとは身体的問題だけではなくて、内面的にも追い込まれている状況を指し示している。従って、医療チームには、家族に対して患者さんとの接し方の助言だけではなく、家族の全人的痛みにも向き合う態度が求められる。
しかし、医師や看護師は、今でも多忙をきわめていて、心では思っていても実際には時間が取れない。このことは、彼らのバーンアウト(燃え尽き症候群)の原因の一つにもなっているのが現状である。そこで、その役目は臨床心理士やカウンセラーや医療ソーシャルワーカーの仕事になるが、一部の緩和ケア病棟を除いて、すべての病院に配置されているかというとそうでもない。それどころか、配置されていたとしてもあまりに少人数で、患者さん本人に対するだけでもオーバーワークになっている。実際、宗教家(チャプレン)として要請を受けて出向いてみると、どちらかというとソーシャルワークであったりすることも多い。このような医療現場では、患者さんのご家族の悩みを把握して誠実に向き合う時間がなかなか取れないのである。
だからといって、何もしないのではない。三十八歳で臨終を迎えた女性患者の例を見てみよう。二ヶ月ほどのおつきあいであったが、最初の面談で残してゆく家族への思いを訴えて号泣し、看護師さん共々もらい泣きしながら聞いた。そして、翌日から患者さんの依頼で家族ケアを行うことをチームで確認した。
■内面的な痛みにどう向き合うか
まず、夫との面談では、「私は奇跡を信じたい。しかし、今後のことや特に妻なき後の子どもたちの将来についても話しておきたいが、そうなるとどうしても死を話題にすることになるので、妻がショックを受けるのではと不安があって、とてもできそうもない。」と涙ながらに話した。
中学三年生の長女には、患者さんの希望で、母親の厳しい病状を丁寧に伝えた。その夜自宅に帰って、一晩中膝を抱えて泣いていたという。この子はその後母親の介護に励んでくれた。ただ、病棟としては、バーンアウトに注意することを申し合わせた。それは、なくなられる十日ほど前に起こったが、チームの支えで何とか乗り切ることができた。小学二年の二女は、なくなる二週間ほど前に、父親に「人は死んだらどうなるの」とたずねた。深夜、辛かったと父親から電話があった。母親がどこにもいなくなるという不安を訴えたのである。
五歳の長男は、お母さんが長いこと入院で寂しいね、といわれると、「ぼく、叔しくないよ」と答える。しかし、朝、保育園に出かけるとき、祖母に「ぼくの枕洗ったらだめだよ」という。彼は、母親の枕で寝ているのである。
このように家族の痛みが現われる。そして、家族は闘病中だけの苦悩ではなくて、死後も妻、母のいない人生を歩まねばならない。家族ケアが必要なのである。
■悲嘆ケアは僧侶本来の役目
今回はグリーフケアについて考えてみたい。
グリーフケアとは悲嘆ケアのことである。大別して、間もなく訪れるであろう臨終を予期せざるを得ない患者さんと、その家族のさまざまな苦悩に対して行なわれる予期悲嘆ケアと、亡くなられて後の家族が喪失の痛みを抱えて生きることへの援助として行なわれる悲嘆ケアがある。
その内容や具体的な援助の方法は、緩和医療関係の書物に紹介されているので、そちらを参照していただくこととして、ここでは、医療と宗教との連携という視点から少し考えてみたい。
まず、予期悲嘆ケアは臨終を迎えるまでのことだから、当然病院の中のケアである。ただし、緩和ケア病棟を除いて、治療中心の病院では意識的に行われているとは言い難いのが現状であろう。
しかし、医師や看護師との雑談の折にはしばしば話題になるので、無意識のうちに対応してはいると思われるが、ケアの要素にはなっていない。そこでは、受容的に傾聴することや自分の価値観を相手に押しつけない態度は当然のこととして、患者さんやご家族の問いを待ったうえで、死を話題にできる力や、自分自身の死生観をある程度日常的に考えておくことが必要であるが、現在の医療事情ではそんな余裕はあまりない。
したがって、予期悲嘆ケアを意識する病棟は、僧侶に対してこうしたケアの役割を期待することになるが、そうした施設も参加する僧侶の数も少ない。心ある医療者だけで、しかも個人的に行われている状況である。
こうして臨終を迎えた患者さんや家族は、病院から自宅や葬儀社に送り出され、それぞれの宗派で通夜、葬式、中陰などの仏事、法事が営まれることになる。そこで、ほとんどの家族は初めて仏教に触れることになる。その際、僧侶のことばに励まされた。などのうれしい感想をたまには耳にするが、多くが儀礼的になされていると言っても言い過ぎにはならないだろう。
最近では、宗教者の介在しない葬儀も増えているといわれる。現代人の宗教心の無さを嘆くよりも、宗教不信の現われと僧侶の側が反省すべきことである。だからこそ、喪失の痛みを学び、家族に寄り添い、ゆるやかな再出発を援助するグリーフケアも僧侶の本来の役目のひとつといえるのではないだろうか。
■死後届いたハガキが家族をケア
「いつもいっしょにいるよ」と、生前の夫によって書かれたハガキを肌身離さず持っている奥さんがいる。死後一ヶ月たって、病棟の看護師から送られてきたものだ。何よりも励みになっているという。これなどは僧侶の仕事に思えてならない。
グリーフケアではないが、最近の葬儀で、四十九歳の父親を見送った高校二年の息子さんの弔辞を聞く機会があった。幼い頃の父親とのエピソードを、彼は号泣しながら遺影に語りかけた。そして、最後にこう叫んだ。
「俺たち、住職さんからいつも聞いていたよね。お父さん、仏さんになったら、みんなを助ける人になるんだよね。忙しいだろうけど、仕事好きだったから大丈夫だよね。お父さん、そっちでがんばれよ。俺もこっちでがんばるからさ。また会おうね、ありがとう」
父親の生前、法事のたびに病棟での経験を話してくれと依頼してきた家族であった。
■僧侶は生前に、医療者は死後に関わりを
患者さんと家族の生前のプロセスを僧侶が学び、そして死後の家族の心の軌跡を医療者が学ぶことを通して、死の一点でバトンタッチする寂しい関係から、相互に協働する温かい連携が生まれると思っている。
連載にあたって・・・ 終末期医療の現場で活躍する僧侶の奮闘記―。今日から、長倉伯博(ながくら・のりひろ)浄土真宗本願寺派善福寺住職(51歳)=鹿児島市福山町=の連載が始まります。日本緩和医療学会会員の長倉住職は、地元の鹿児島で医師や看護師らと「かごしま緩和ケア・ネッチワーク」を立ち上げ、医療チームの一員として患者や家族のケアに日々取り組んでいます。 |