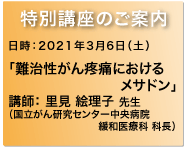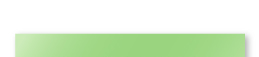
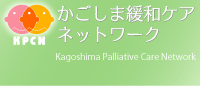
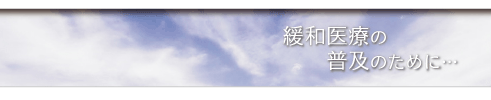
トップページ > 緩和ケアに関する情報 > 宗教的ケア
![]() 坊さん奮闘記3 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
坊さん奮闘記3 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
■お坊さんに聞いて欲しかった
今回は私が最初に出会った五十八歳の患者さんとその奥様のことである。十五年前のある日、突然に電話をもらった。
「患者さんの相談に乗ってくれる坊さんがいるが、会ってみないかと話したら、ぜひ会いたいといううちの病院に来てくれないか」
ビハーラ活動を始めて間もないころで、ある寺の門徒さんが院長や看護部長である病院とか、私の個人的な知人の紹介であったりとか、そんな小さなつてを手がかりにして、宗教が医療に参加する意義を訴えるため、時間を見つけては県内各地をパンフレット片手に訪問していたので、とにかくうれしい要望だった。喜んで返事した。
「近々伺います」
近々じゃ困るんだ。今日か、明日。でないと話ができなくなる恐れがある。おそらくあと一週間ぐらいしか持たない状態なんだ」
気楽に構えていた私は、思わず緊張した。
そして約束通り翌日伺った。受付で来院の意味を告げると、すぐに主治医である院長室に案内してくれたが、他の医師や看護師が訝しんでいることは視線でわかった。看護師長、担当看護師を交えて、これまでの経過と現在の状健を確認した。この二年間に三回手術をし、その度に退院できたので、今回も本人は手術を希望していたが、とても無理な状況だ。人柄を考えると、嘘をついたまま臨終を迎えさせることには抵抗がある。だから、無理な手術は避けて、最後の時間を大切に過ごしてほしいと本人と奥さんに話した。正直に教えてくれたことには感謝しているが、何か悩んでいるようだから僧侶である貴方のことを紹介したら、ぜひ会いたい、というので来てもらうことになった、とこれまでの経過を話してくれた。
病室で最初は互いのことを紹介しあったが、途で意を決したように彼は話し出した。
「私は地獄に往きます。住かなければならないのです。お坊さんに来てもったのは、死んでから極楽に往きたいとか、安らかに死にたいと思っているのではないのです」
「では、どうして私を選んだのですか」
「人をいっぱい傷つけて生きてきた私の人生を誰かに話しておきたかった。身勝手かもしれないが、お坊さんが一番ふさわしいと思ったのです」
■最期の病床に人生語り、話し終え柔和な表情に
彼は目に涙をためて、若い時からの人生を、時折詰まりながら話した。
私は、相づちを打ちながら、彼の表情に注目した。話し始めは緊張していたが、そのうちに赤みが差し柔和になっていくのに気付いた。話し終えると、「こんなばかな男の人生を聞いてくれてありがとう、よかった」と手を差し出した。
私も手を握り返し、お役に立ててよかった、と応じた。そのあと、「他にお辛いことはないですか」とたずねると、しばらく考えてベッドの脇でずっと沈黙していた妻に目を遣り、「こいつの神経痛が心配です。私が死んだ時、子どももいない妻が一人で神経痛を抱えて生きていくと思うと申し訳なくて」と言う。しばらく、うつむいていた妻が、「私、あなたと一緒になってよかった」と叫ぶように言って夫の膝に身を投げ出した。私は、二人をそのままにして静かに病室を出て、経過を医師に報告した。その時涙ぐんでいた医師は、後に僧侶が参加した症例として医師会報に載せてくれた。
■当初は「坊さん」に抵抗感
前回の患者さんをみとってひと月たたないうちに、同じ病院から、また依頼があった。出かけてみると、病院の応対が前とはずいぶんと違って、病棟の医師や看護師がにこやかに迎えてくれた。一週間たったころ、顔見知りになった若い看護師さんに、その理由をこっそりたずねてみた。すると、彼女は言いにくそうにしながら、次のように話してくれた
院長から、坊さんに来てもらうことにした、患者さんの了承は取ってある、と朝の打ち合わせで聞いたとき、一同あぜんとした。確かに、前日、手術は不可能、予後はそう長くはないと時間をかけて告知したことは知っていた。しかし、いくら患者さんが落ち込んだからといって、医療者としては素人の坊さんを呼ぶことはないだろう、というのがみんなの雰囲気だった。だって、坊さんといったら訳の分かない説教をするか、テレビに出てくる霊能者のようなことをするのだろうから、もし患者さんの容体が悪化したときはどうするつもりだろうと不安だった。私だけでなく、みんな怪しんでいたのだという。
それがどうして変わったの、とさらにたずねると、いかめしい顔で来るかと思ったら、にこにこ笑って、普通の格好で来たことにまず驚いたという。そして、病院の症例研究会で経過が報告され、患者さんと奥さんのこと聞いたときには感動してしまった。それで、今回は院長からではなく、みんなの声で来てもらうことになったと話してくれた。
もちろん、うれしい反応であったが、一方ではプレッシャーにもなった。うまくいったから歓迎する、もしそうでなかったら来るな、変化がないなら来なくてもいいということでもあるからだ。評価の尺度は私の方には全くなくて、医療の側にあった。この時期の病棟の私の迎え方は、どこでもおおよそこのようなもので、それはしばらくの間続いた。
今は、少し違っている。
■今はケアチームの一員に
ターミナルケアは、全人的痛み(身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな痛み)に対応するという性格から、個人プレーではなくて、宗教家やボランティアを含む多職種がチームとして機能することが要請される。僧侶もチームの一人としての自覚が必要となり、患者さん、家族を含む「いのちの共同体」に参加するのだと現在の私は考えているし、医療の側もそのつもりで迎えているようである。
■相互に学び医療側に変化
実際、ベットサイドでは期待されるほどにうまくいかないことも多いが、それは患者さんの容体や気分に左右されることもあるし、表面化しない悩みを抱えている場合もあるし、またもちろん私のコミュニケーションの取り方に起因することもある。ただ、そうした時でも病棟の症例研究会で検討し、相互批判も交えながら、患者さんとその家族に少しでも人生最期の良い時間を過ごしてもらえるように皆で努力している。
だかう今は、うまくいかなくてもすぐに来るなとはならない。ただ、そうなるまでには、しばらく時間が必異だった。医療者も私自身も、ターミナルケア、緩和ケア、ホスピスケアについて学ばねばならないことがまだまだ多くあった。そのために、全職種、もちろん宗教者も参加した「鹿児島緩和ネットワーク」を医療者たちと立ち上げることになったが、それはだいぶ先のことである。
この病院ではたった二例だったが、その後医療機関からの招きが増え、同時に、症例に対し真剣に学ぶ医療者とともに歩みたくなった少し本気の私がそこにいたのである。
■本人の悩みの整理から出発
僧侶が病棟に出かけるというと、患者さんやご家族に仏教的な考え方を紹介するとか、法話などをしていると思っている方も多いだろう。確かに、聞く準備ができていて、それを期待している方がいるのも事実である。しかし、私の経験からすると、そんな方はごく少数に思える。
実際は、WHOのいう全人的な痛み(身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな痛み)が複雑に絡み合って、患者さん本人も、ご家族も、医療者も葛藤している状態の中で訪問する場合が多い。そこでは、問題は一つではなく、病気が原因になって多くの悩みを抱え込んでいるという形容のほうが適切である。
だから、最初の面談の際に、「今、一番辛いことや困っていることは何んですか」と尋ねることが多い。そして、「その次にお辛いことは?」と言うふうに会話を続ける。これは、私が知りたいという以上に、本人の心の中で悩みの優先順位を考えてほしいからである。つまり、問題の整理から出発するのである。すると、医療に対する不安や不信であったり、家族関係の問題であったり、仕事に対する悩みであったり、そのほか様々な問題が浮かび上がってくる。
僧侶が出向くのだから、生死の問題だけだと考えるのは早計である。一つ一つ、具体的、個別的な会話を重ねながら、その上で、いわゆるスピリチュアルな痛みが訴られることの方が多い。
六十三歳の男性患者さんを紹介する。この方は余命一ヶ月と診断されていたが、結果的に四カ月お付き合いした。若いときに妻と二人で会社を起こし、県内有数の会社に育て上げた社会的には成功者であり、そういう人らしくごうほう豪放らいらく磊落な性格の方だった。数回、病室訪問をするうちに、「若ボンさん、若ボンさん」と私のことを呼び、訪問を楽しみにするようになってくださった。看護師長が、「あなたのことを気にいったと言い出したから近いうちね」と話してから、間もなく心の内を吐露し始めた。
まず、幼いとき、里子に出された辛い思い出話だった。兄弟の中でなぜ自分だけ出されたのか、小学枚の帰り道に実家がみえる山の上から、貧しい暮らしながら実母にまとわりつく兄弟たちのはしゃぐ声を聞いて、近くのお寺の縁側でひとしきり泣いてから、養子先に帰った、という。実母にも孝養は尽くしたつもりだが今も複雑な思いだと、笑うなよと照れながら涙ぐんで話した。そして、私を見て、ボンさんが泣いたらシャレにならんぞと笑った。この日から私たちの距離はだいぶ縮まったのである。
■具体的、個別的会話重ねて
それから数週間して、ある日会社のことを話題にした。それは、大変誇らしげであった。しかし、最後にあと三年命が欲しいと叫んだ。息子たちは技術の面は大丈夫だ、だが経営をまだ知らない、それを教えていないと唇を噛んで話した。
亡くなる二ヵ月程前に、一度危機的な状態があった。医師たちの努力で脱したが、この日を境に少し変化があった。妻に、お前と本当に夫婦らしくなったのは入院してからかもしれんな、今まで仕事仕事できたからなあ、としみじみいう。妻が、一日一日大事にしましょうね、と応じると素直に頷いた。
■精一杯の笑顔で握手
亡くなる前の日、危篤という病棟からの連絡で深夜駆けつけると。「死ぬとはどういうことかなあ」。少し間を置いて「世話になったな、先に往って待ってるぞ、あんたのこの仕事は大事な仕事だぞ、身体に気を付けるんだぞ」と途切れ途切れに話しながら、にっこり笑った。私も精一杯の笑顔で手を握り返した。妻が横で泣いていた。
連載にあたって・・・ 終末期医療の現場で活躍する僧侶の奮闘記―。今日から、長倉伯博(ながくら・のりひろ)浄土真宗本願寺派善福寺住職(51歳)=鹿児島市福山町=の連載が始まります。日本緩和医療学会会員の長倉住職は、地元の鹿児島で医師や看護師らと「かごしま緩和ケア・ネッチワーク」を立ち上げ、医療チームの一員として患者や家族のケアに日々取り組んでいます。 |