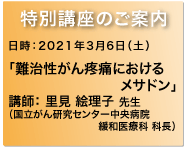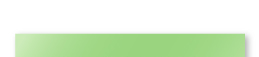
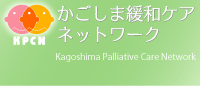
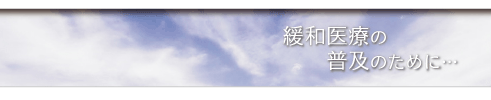
トップページ > 緩和ケアに関する情報 > 宗教的ケア
![]() 坊さん奮闘記2 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
坊さん奮闘記2 本願寺派善福寺住職 長倉伯博
■安楽死、自殺幇助、嘱託殺人の依頼
今回からは、今までに出会った患者さんや家族、医療者の方々とのお付き合いを古い方から現在に至るまで順に紹介しようと計画していて、この方のことは連載の先の方でと考えていた。しかし、一本の電話で私の気持が高揚してしまった。それで、順番を入れ替えて今回紹介することにした。四月初めのこと、外出先から少し遅めの帰宅で、いつものように留守番電話のメッセージを聞こうとボタンを押した。すると、「合格しました」という声が流れてきた。思わず、もう一度聞き直した。そして、彼の声に間違いないと確認して、受話器をじっと見つめながら、私は九年前の春をしきりに思い出していた。
電話の彼は現在三十五歳になるが、当時は二十六歳。塗料会社の役員をしていた父親の仕事の縁で、塗装工として家族を支えていた。そのころ、彼の父親は五十歳で、十六年にわたるガンの最終段階にあり、その年の六月には臨終を迎えることになる。
それから四年後、その彼が思い立って、まず准看護師の資格を取り、結局五年がかりで正看護師になったというのである。三十歳にもなって、それまでとは全く方向の違う分野の仕事を志し、十歳以上も年の離れた同級生と机を並べ、アルバイトをしながら苦学の果てに成し遂げたというだけでも称賛に値するが、その努力の陰に今は亡き彼の父親の存在が思われてならないし、彼自身の口ぶりからもそんなことがうかがえるのである。
記録では父親の最初の手術は、彼が九歳の時。元気な父の姿はあまり記憶にないという。最初は直腸と大腸のガンだった。その後十六年間に大小二十五回の手術(本人、家族のことば)を受けた。亡くなる前年の暮れには、「春の桜までは無理かもしれない」と告知されたが、三月の末になって、まだ持ちこたえていた。しかし、下肢まひで、疼痛の訴えは強く、そのせいか不眠も続いていた。
■「死なせてくれ、殺して欲しい」
そのころ、大学病院の麻酔医から連絡があった。「患者さんの相談に乗ってくれる坊さんがいると話したら、ぜひ会いたいという。最後は自宅で迎えたいとの本人の希望で、今は在宅ケアチームを組んでいる。少し遠い所だが出かけてくれ」との依頼だった。
その医師に案内されて四月三日が最初の訪問。それから彼の父親との付き合いは六月二十四日午前零時五十三分まで続くことになった。
お互いに紹介がすみ、二人きりにしてもらった。
「あなたに人生最後の頼みがある。お願いだから、死なせてくれ、殺してほしい。自分で死のうとしたが今はその力さえない。一休さんや良寛さんをはじめ、お坊さんは困った人を助けてくれたじゃないか。私を救うと思って手伝ってくれ。ここにどれほど死にたがっているか書いておいた。これがあれば、最悪でも執行猶予ですむだろう」
そう言って、彼は目に涙をためて、一枚の紙を差し出した。今思うと、安楽死、自殺幇助、嘱託殺人の依頼である。
■励ましにあまりに意味のない状況
こういった際に、気弱になるなとか、もっと明るいことを考えろとか、人間はだれもがいつかは死ぬんだからがんばれとかの励ましはあまり意味がないことは、それまでの私のささやかな経験が教えてくれていた。だから、どうして死にたいのか、殺してほしいのか、もう少し話してくれないかと頼んでみた。
彼は胸の内を吐露し始めた。
■聞き続けて変化する関係
「妻は、今日で四日もろくに寝ていない。夜中に気が付くと身体をさすってくれている。今までにも何回もこんなことがあった。私が死んだ後、看病疲れで倒れるのではと思う。もういい加減に妻を楽にしてやりたい。病気になってから十六年もこんな男につき合ってくれて心から感謝している」
「子どもたちもこんな生活のなかでよく成長してくれた。でも、五十歳の親父が、二人の子どもの稼いでくるお金で生活しているなんて話がどこにある。それなのに、給料日になると、そっくり妻に渡し、お父さん今日はすきやきでも食べようか、と声をかけてくれる。もう充分です。自分で稼いだお金は自分で使わせてやりたい。お願いです、私を死なせてください」
彼は目に涙をためて、絞り出すように話した。胸が熱くなった私は、彼の手を握り締めたまま、言葉を失った。
「あなたにとって、自分の命より何より大切なご家族なんですね」
しばらくして、私がようやくロを開くと、彼はうなずきながら涙を溢れさせた。そして、こんな辛い話を聞いてくれてありがとう、という。
■何を語るかという前に共感し受け容れる努力を・・・
私は、その時彼の表情の変化に気がついた。最初に比べると、とても穏やかになっている。聞く内容はとても辛いが、話し続けるうちに楽になった様子がうかがえる。
実はベッドサイドにいると、こういう経験をすることがある。死なせてくれ、という言葉に直接答えることは難しいが、心を傾けて聞き続けることで、相手と私の関係が変化するのだと受け止めている。辛い話が心の中から言葉として表に現われるとき、それは信頼の扉が開きかけた証左といってもいいだろう。
宗教者の臨床活動も、このことが前提になって初めて可能になる。何を語るかという前に、共感し受け容れる方にこそ努力を傾けることが求められている。人生の意味や生死の問題などのスピリチュアルな問いは、その後に顕在化してくることが多い。
最初の面談から一ヶ月ほどして、長いこと親の命日にお参りしていないから、お経を読んでくれという。医師や看護師に手伝ってもらい、車椅子で移して仏間に連れていった。お経が終わると、その中にはどんなことが書かれてあるかと問うた。私は、お経の成立から話し、倶会一処、極楽浄土でまた会えるよ、私も必ず往くから、というようなことを話した。
「本当をいうと、お坊さんにもっと早く会っておけばよがったと後悔していたけど、また会えるんだ、良かった、この世では短いけど、長い付き合いができるんだな」
彼が手を合わせると、そこに居合わせた医療チームも静かに手を合わせた。それから、一カ月ほどして、いよいよ臨終の日がきた。医師からの知らせで、間に合わないと思いながら、車を急がせた。着いてみると、瞳孔は開いて意識はないという。手には不規則なけいれんがあった。その手を握り締め、今着いたよ、と叫んだ。あらためて瞳孔を確認した医師が、驚いて意識が戻っているという。家族がそれぞれに、父観への感謝を告げた。言葉を発することはできないが、目尻から涙が一筋流れた。そして笑顔が浮かんだ。
医師が臨終を告げた。誰からともなく、拍手がわいた。見渡すと皆涙を流していた。
連載にあたって・・・ 終末期医療の現場で活躍する僧侶の奮闘記―。今日から、長倉伯博(ながくら・のりひろ)浄土真宗本願寺派善福寺住職(51歳)=鹿児島市福山町=の連載が始まります。日本緩和医療学会会員の長倉住職は、地元の鹿児島で医師や看護師らと「かごしま緩和ケア・ネッチワーク」を立ち上げ、医療チームの一員として患者や家族のケアに日々取り組んでいます。 |